司法書士試験について、今回はマイナー科目である「憲法」の対策法について話していきます。
憲法は、出題数が3問と少ないにもかかわらず、割としっかり勉強しないと点が取れない科目です。正直なところ、コストパフォーマンスは良くありません。しかし、司法書士試験で求められる憲法の知識は、特に判例の正確な理解にあり、当てずっぽうでは答えが出せない問題が出題される傾向にあります。
この点、最近は一般常識でどうにかなるようなクイズ大会のような問題が出ている刑法とは異なり、憲法は知識を整理して深く学ぶ必要があるのです。
この記事では、過去問が少なく対策が難しい憲法について、私が実践していたテキストを重視した学習戦略を中心に、人権と統治それぞれの具体的な勉強法を詳しく解説していきます。憲法対策に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
憲法はしっかりとした勉強が必要
憲法に関しては、割としっかり勉強しないと点が取れるようにはならないですね。だから、コスパは正直良くないんですよ。
3問しか出ないにもかかわらず、割と聞かれることが、ちゃんと知っているかどうかというところを問われるんで、特に判例ですね。判例知識に関しては、しっかりその判旨というのを分かっていないと答えが出ないんですよね。当てずっぽうでは答えは出ない。
刑法と並べて語られることもありますが、近年の出題には易しめの肢も見られます。もっとも年度差があるため、刑法も頻出論点を過去問ベースで押さえる前提で、憲法の学習配分を検討するのが現実的です。
一方、憲法は基礎知識と判例理解を積み重ねる必要があります。
過去問の状況と現在の出題傾向
しっかりやると言っても、やっぱり主要4科目ほどはやりません。パラパラ教科書を読みながらということにはなるんですけれど、だからと言って、過去問が充実しているわけでもないんですよね。
平成17年か18年に、憲法というものが司法書士試験の中に組み込まれてから、やはり歴史が浅いんです。なので、20年分すら過去問がないという状態で、しかも「推論問題」。
現在の傾向では出題されにくい推論問題もたくさん収録されていて、一時期本当に憲法といえば推論問題ぐらいの時代があったぐらい。今の傾向とは本当に異なる問題ばかり収録されているんですね。
推論問題は平成28年を最後に頻度が下がっていますが、年度によって再出題される可能性もあります。直近10年の過去問を確認しながら、基本知識と主要判例を優先する方針が効率的です。
本当に基本的な知識をしっかり正確に覚えているかというところが、憲法では大事になるかなと思います。
テキスト重視の学習法
過去問があまり充実していないので、ではどうすればいいんだろうということなんですけれども、やっぱり私は「テキスト重視の学習」がいいかなと思っています。
薄いテキストを主軸に、①平日は5〜10分のミニ復習(判例要点カード化・間違いノート)を行い、②週1回はまとまった演習で定着を確認する、という二段構えが効果的です。
人権分野の勉強法:判例の理解を深める
人権のところに関しては暗記ではないんですよ。暗記では済まずに、判例、各人権に関しての判例をしっかり突き詰めて、この判例ではどの人権が問題になっているのかというのを逐一確認しながら判例を読むことです。
判例を読むときには、「この判例ではどの人権が問題になっているのか」「どういう理由で判断されたのか」を逐一確認することが重要です。判例1件ごとに①争点人権→②判断枠組→③結論→④キーワードを20〜40字でまとめ、翌日と1週間後に再現チェックする形で反復すると、理解が定着しやすくなります。
ああ、なるほどな、これはあの「法の下の平等」の判例なんだ、とか、私人間効力の問題なども、憲法が直接的に適用されているのではなくて、民法が間接的に適用されているといったケースがあります。
人権の問題もそうなんだけれども、そういうふうに他の法律との繋がりみたいな話も出てくるんです。ここは論理的というか、理論的な部分で、しっかり判例を読み込んでいないと分かりにくいところがあるんですよね。
例えば、「取材の自由は尊重に値する」とか、「尊重すべきでメモする自由も尊重に値すべき」といった感じで、ただちょっと文言が若干違うといったところがあります。また、「報道の自由は保証される」といった、その辺の細かいところまで結構聞いてくるイメージがあるんですよ。だから、しっかり判例を読み込むことが大切です。
判例百選などの専門資料は、基本的には必須ではありません。テキスト中心で十分対応できますが、理解が浅い箇所のみ補助的に確認する“点検利用”にとどめると効率的です。
私はテキストとしては「ブレイクスルー」を使ってましたが、基本的にその司法書士試験において必要な判旨は教科書中心で対応できることが多く、無理に周辺資料まで広げる必要はありません。
私の場合は、範囲を広げすぎると効率が落ちました。
なので、やっぱり教科書に引用されている判例の文章をちゃんと読むことが大切になると思います。暗記するというよりは、この内容って、この判例って何の人権が問題になっているんだろうな、そしてどこを重要視したんだろうなっていう感じで、裁判官の気持ちになって判例を読んでみると、また違った視点で理解が深まるかなと思います。
手を広げすぎないことの重要性
過去問が少ないからといって行政書士や司法試験の問題まで広げすぎると、効率が下がります。他資格の過去問は原則不要で、理解が浅い条文・判例を補う目的で1〜2設問だけ確認する程度にとどめましょう。
憲法なんてやり始めたら、とことん追求できる、探求できる科目なんですよ。本当に司法試験で言うと、答えがない、終わりの見えないような学問として知られていますけれども、本当に泥沼だなって思うんですよ。
だけども、試験対策上の憲法というのは、判例クイズみたいな感じなんですよね。
すごい割り切って勉強してしまえば、すぐに点に繋がるという感じで、教科書をメインに据える方針が有効だと感じています。教科書も全然分厚くないんで、薄いテキストだけれども、徹底して読み込めば、安定して得点しやすくなり、理解が進むと答えにたどり着きやすくなることがあります。
やっぱ結構強烈な事件が多いんですよね。割とこう人格を蹂躙させたとか、そういう文言がかなり強烈ですから、ストーリーとして覚えると頭の中に入ってきやすくなるんですよね。そういう意味で、イメージしながら判例を読むというのがすごい大事。
そこが何より大事で、過去問に手を広げて、行政書士の過去問やら何やらってやっていたら、どんどんやらなくていいところばかり覚え出すというところで、合格が遠のく。もちろんやるに越したことはないし、そこで何かメソッド得られるのかもしれないけれども、やっぱ憲法に使っている時間なんてないですからね。
やはり主要4科目の時間が優先になりますが、憲法も毎日少し触れることが大切です。最低限、平日は5〜10分でもテキストの要点を確認し、時間が取れる日は45分ほど読書型で復習するなど、習慣的にコツコツ進めるのがおすすめです。
マイナー科目全般に言えることだけれども、やっぱり割り切って、「この薄いテキストだけ」に絞ってやろう、というのがおすすめです。主要な出題は教科書範囲が中心と感じました(例外あり)。
変化球の論点に時間を割いても多くの受験生が取りづらいです。そこで行政書士の過去問解いていた人が受かったとか、司法試験の過去問解いていた人が受かったとか、択一六法を使ってた人が受かったとか、私の周囲では事例を多くは見かけませんでした。
やはりブレイクスルーならブレイクスルー、オートマならオートマって感じで、自分の持っている教科書を本当に読むこと。読書感覚でもいいので、内容を理解することに終始すれば、人権は高得点を狙いやすいと感じました。
統治分野の勉強法:条文知識の暗記
「統治」については正直暗記です。高校の社会で習ったようなことがたくさん出てくる。例えば裁判官の任期とか、定年退職の年齢とか、衆議院参議院の任期というか、解散等の仕組みなど、本当に高校の社会で習ったようなことばっかりを聞いてくるんですよね。
どこを聞いているかというと、やっぱ条文知識。割と統治に関しては条文をメインに勉強してもいいのかなと思うんですけれど、やはりそれもコスパが悪いんですよね。
捉え方によりますが、どれだけやっても1問しか出ない統治だなっていうのか、いや別に高校社会レベルに暗記するだけで1問取れるんだったら俺は得点源にするぜという考え方もあるし、人それぞれ。
私の場合は、高校の社会は別に苦手じゃなかったんで、パラパラ条文読んで、統治分野については、私が受けた年は比較的易しめでしたが、年度によっては難問が出ることもあります。財政に関しての条文の知識が出たりしたんですけど、たまにすごい変な問題が出るんです。
例えば地方自治などが出ると、多くの受験生が難しく感じることがあります。
一時期、地方自治の問題がやたら出てた年があったんですよ。2、3年連続ぐらいでね。そうした傾向は近年少ないものの、出題は年度で変動することがあります。過去問の頻度を確認しながら、配点や学習時間のバランスを調整していくとよいでしょう。
とはいえ、時間をかけすぎると他科目に支障が出るため、私は統治分野を頻出条文(任期・内閣・裁判所・財政など)中心に絞りました。
年度差への保険として、直近の過去問で出題が増えた条文だけは補足して確認するようにしていました。
憲法対策のまとめ
まとめると、以下のようになります。
- 人権に関しては判例を読み込んでストーリーを意識した理解をする。どの人権が問題になっているのかを逐一確認しながら読むと理解が深まる。
- 過去問も一応ある分に関しては解いた方が良いが、「推論問題の優先度は低めにする方針も考えられる」。
- 統治に関しては、頻出条文(任期・解散・裁判所・財政など)を中心に暗記するのが効果的。
- 三権分立などの概念的論点は出題が限定的だが、直近過去問で出題が増えている領域があれば、例外的に追加確認しておくとより安心。
この方針で得点しやすくなる可能性があります。
最後に、合格に向けた1つの戦略として、時間配分の観点で学習比重を下げる選択肢もあります(他科目との総合戦略次第)。
どうしても憲法が得意にならなくて、苦手なままという人もかなり多いんですよね。私は憲法割と得意だったんで良かったですけど、その分刑法は苦手です。
憲法を捨てれば、刑法はもちろん満点取らなきゃいけないというリスクがあるので、その辺も結構自分と相談しながら勉強法は考えていただければなと思います。
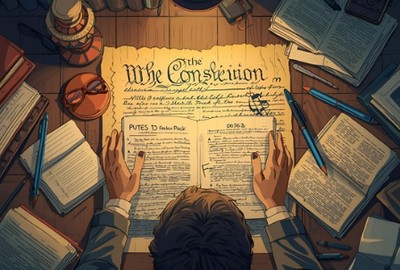


コメント