今回は司法書士試験対策として、刑法を掘り下げてお話ししたいと思います。
もうこの試験を乗り越えて振り返ってみると、刑法って午前の部の筆記試験でたった3問しか出ないんですよね。その3問のために、どれだけ時間と労力をかけるべきかって、本当に悩ましいところでした。
この記事では、そんな刑法の学習について、私が実際に使っていた教材から、どこに重点を置いて勉強を進めていたのか、そして「あくまで私の場合では覚えなくても支障がなかったな」と後になって分かったポイントまで、お伝えしていきます。
刑法はマイナー科目ですが、だからこそ効率の良い対策がカギになるんです。ぜひ、私のちょっとした経験談を、皆さんの勉強のヒントにしてもらえたら嬉しいです。
私が刑法対策で選んだ教材と心構え
教材は「定番」でシンプルに
まず、私が刑法対策に使った教材ですが、これはもういつもの流れというか、定番を外さなかったですね。
私は市販のオートマシリーズを中心に学習しましたが、他の主要教材でも同様の学習効果が得られると思います。
正直なところ、使っていた教材の話はこれでおしまいなんですよ。シンプルにテキストと過去問を繰り返すというスタイルでした。
優先度に応じた目標設定
私自身は、最低でも2問を安定して取れるように意識していました。
得点目標は人それぞれですが、過去問分析を踏まえて現実的なラインを決めると良いと思います。
1問しか取れないとなると、ちょっと厳しいかなという気持ちがあったので、私は“2問を目安”に据えていました。目標は人それぞれで、過去問分析に基づき調整するのがおすすめです。
この割り切りが、マイナー科目を学習する上では結構大事だった気がします。
実際、本試験の直前期には、週1の演習デーに加え、平日は5〜10分の“ミニ復習”(間違いノートや肢別の見直し)というやり方にしてました。
民法や不動産登記法など、配点の高い主要科目に時間を割くため、刑法は後回しにせざるを得ませんでした。だからこそ、その週一回の演習で、優先的に2問分の主要論点を確認しておく、というルーティンが私には有効でした。
民法との「読み込みレベル」の圧倒的な違い
3問しか出ない科目だったということもあって、正直、民法と比べるとめちゃくちゃ読み込んだかというと、そうでもない、というのが本音です。やはり、時間の制約の中で、どうしてもリソース配分は民法や不動産登記法などの主要科目に偏ってしまっていましたから。
今、こうして振り返って、手元の参考書をバーっと見てみると、「あれ、これ頭に残ってないな」というところが結構いっぱいあるんです。本当に。
行政書士の勉強をしていて、民法の教科書とかをパラパラ見返したりするんですが、その時の民法との読み込みレベルの差は、もう雲泥の差なんです。民法とかだったら、もう論点の流れが全部頭の中にほぼ入っている状態なんですよね。だから、読み進めるのにそんなに時間がかからないんです。
「よし、この刑法のテキスト1冊、読み進めよう!」って思ったら、もう一日じゃ終わらないですね、今の私だと。そのくらいの読み込み具合なんです。
民法の方だったら、この前、昨日と一昨日ぐらいで読んでたんですが、問題集も含めて、1冊を1日で、8時間とか9時間とかで全部パーッと読んでいけるんですよ。行政書士の時でも、民法1だけで8時間ぐらいかかったかな。
それに比べると、刑法は「少しずつ」という感じでした。この差が、そのまま試験の出題数と難易度、そして自分の気持ちの入れ方の差だったんだなと思います。
刑法学習で「やらなくてよかった」こと
条文学習は必要範囲にとどめる
具体的な勉強法としては、教科書と過去問の話に行き着くんですけど、条文は頻出・重要箇所に絞ってテキスト内で確認し、刑罰の数値は原則として優先度を下げ、過去問で出る条文を中心に反復しました。
条文の中には「懲役何年」とか「罰金何年」とか書いてありますよね? 最初は自分も「え、ここ年数まで覚えなきゃいけないのかな?」と思ってたんです。
私が受験した範囲では、刑罰の年数を直接問う問題は見かけませんでした。(年度によっては例外的に出題される可能性はありますね)
覚えるべきは「構成要件」
試験で問われるのは、年数とか罰金の額ではなくて、「この事例は重大な結果を伴う罪に該当するのか、それともその未遂なのか」「共犯なのか正犯なのか」「教唆犯なのか」といった、要件の方なんです。罪の成立要件や、共犯の形態などを問うてくるんです。
私の学習では優先度が低いと感じました。年度によっては数値が問われる可能性もあるため、過去問で確認しつつ判断するのが無難です。
ちょっと予備校とか、他の人がどういうかはわかんないんですけど、数万以下とか、時々執行猶予が何年以下とか、ほんの時々出てくることはあったんですが、私の場合は、全てを網羅暗記せずとも、頻出範囲に集中して対応できました(必ず直近過去問で傾向を確認)。
出題傾向によっては数値が問われる場合もあるため、過去問を確認しながら優先度を判断するのがおすすめです。
結局は「繰り返し」が土台
最終的には、繰り返しを軸に進めるのが有効だと感じました。
刑法って、たまにすごくひねくれたというか、難しい問題も出てくるんです。やっぱり難しかった。覚えることもいっぱいあるし、論点も複雑で。
特に、共犯に関する論点、たとえば共謀共同正犯とか、あの辺りの複雑な事例問題は、最初は何度読んでも頭の中で整理がつかなくて苦労しました。それでも、テキストを読み返し、肢別過去問集で似たような事例を繰り返し解くうちに、だんだんと「要件の枠組み」が掴めてくるんですよね。
最終的には、その「繰り返し」による慣れと、論点のパターン認識が、本試験での判断スピードに直結したと感じています。
そうした難しさに立ち向かうには、やはりテキストと過去問を繰り返し、計画的な反復(小分け学習+定期演習)で知識を定着させるのが最も効率的でした。
まとめ
- 司法書士試験の刑法は午前の部で3問出題され、重要論点を中心に2問前後を安定して取ることを目標とする受験生も多い。
- 使用教材はテキストと過去問集に絞り、繰り返し解くことが知識定着の鍵となる。
- 刑法学習で力を入れるべきは、刑罰の年数や罰金といった数値ではなく、構成要件や共犯など罪の成立に関する論点である。
- マイナー科目であり、民法など主要科目と比べると深追いはしづらいが、出題範囲を絞って効率よく対策することが重要。
刑法は難しくて、私も正直、民法ほどは読み込めていなかった部分もありました。でも、過去問の出題傾向を掴んで、自分には深追いしない方が合っていた部分が分かり、効率よく対策を進められたと思っています。動画を見て「もう一度頑張ろう」と思ってくれた方がいると知って、本当に感謝していますし、私もこの経験を伝えることを続けていきたいですね。
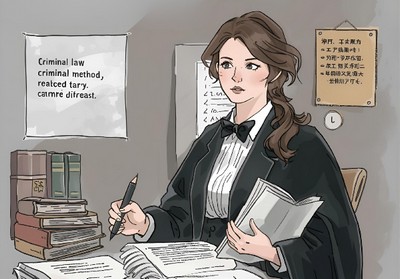


コメント